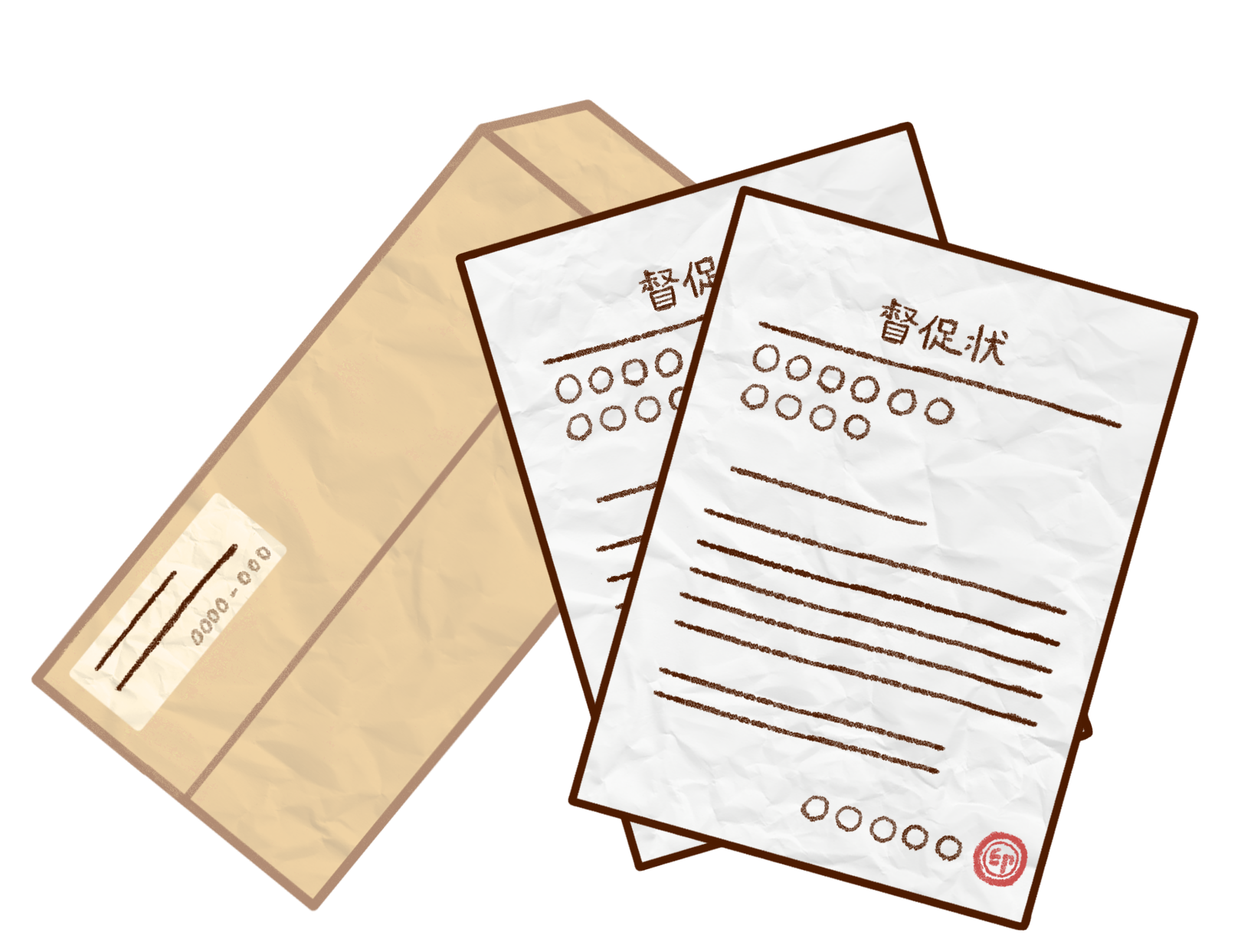この時間は休憩?労働時間?
労働するための準備時間や作業の合間の空き時間、仮眠時間などは、労働時間にあたるのでしょうか?労働時間は原則として1日8時間、週40時間と定められています。準備時間や空き時間も労働時間に含まれるのであれば、それを含めて計算した労働時間が8時間や40時間を超えるのであれば、残業時間となります。労働時間かどうかは、一体どのように定められるのか考えてみましょう。

ポイントは、労働者が使用者の指揮命令下にあるかどうか
この点について、最高裁判所は、就業時間外に行うものとされていた作業服や防護服への更衣、準備体操場への移動、実作業終了後に作業服等を脱ぐ時間などについて以下のように判断しています。
労働時間とは「労働者が、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に決まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによって決定されるべきものではない。」
「労働者が就業を命じられた業務の準備、行為等を事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、または、これを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要なものと認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する(三菱重工業長崎造船所事件ー最判平成12年3月9日・労判778号8頁)。
このように労働時間とは、実作業に従事している時間のみを指すものではなく、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間となり、指揮命令下にあるかどうかについては、客観的に判断される必要があるということです。
例えば、同じ勉強会であっても、自由参加の場合と参加が義務付けられている場合では、客観的に見て指揮命令下にあるかどうかはおのずと異なります。直接義務付けられてはいなくとも、不参加の場合には、何かしらの不利益を強いられると言うような場合には参加を余儀なくされているということですから、労働時間にあたります。
労働時間には、複数の意味がある
ひとくちに「労働時間」といっても、その意味には複数のものがあります。
1 労働基準法上の労働時間
2 労働契約上の労働時間
① 賃金時間(賃金が支払われる時間)
② 労働契約上の労働義務のある時間(所定労働時間)
簡単にいうと、労働契約上の労働時間は労使の合意によって定まるもので、次掲の労働基準法上の労働時間とは一致しない場合があります。例えば、早退した場合でも賃金カットせず、労働したものとして扱うという合意がある場合、早退して労働しなかった時間は、労働契約上の労働時間であり、賃金時間ではあるものの労働基準法上の労働時間には含まれないこととなります。
労働時間が問題となる場合、労働時間の概念を整理して検討することが必要となります。
労働基準法上の労働時間と賃金
労使の合意によって、定まる労働契約上の労働時間と客観的に定まる、労働基準法上の労働時間がある事はわかりました。
では、労働基準法上の労働時間と賃金との関係はどのようになっているのでしょうか?
例えば、労働基準法上の労働時間である限り、最低賃金法が定める時間単価が常に発生すると考えて良いのでしょうか?
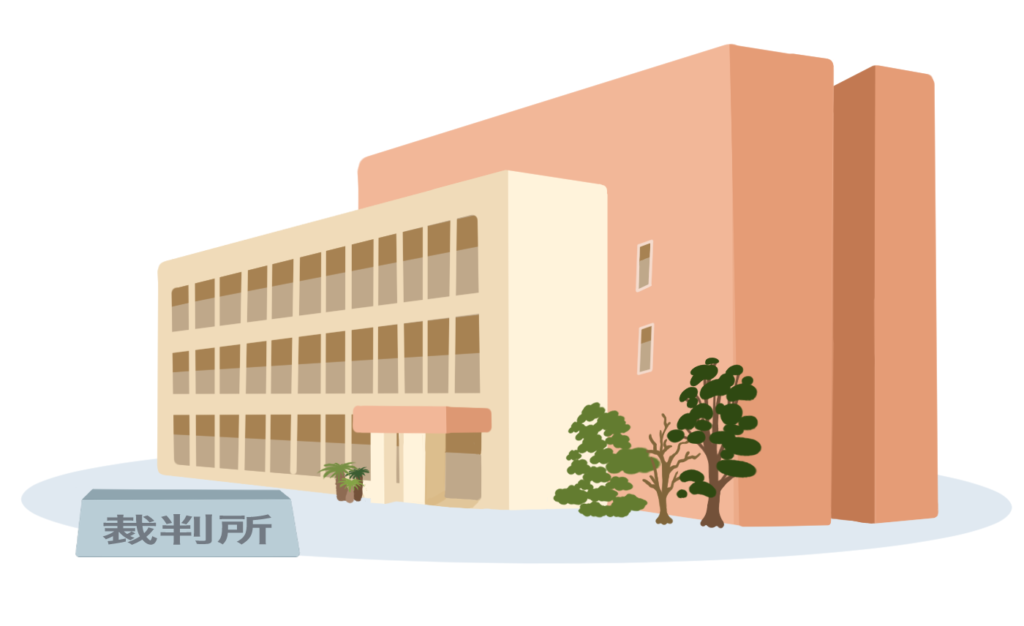
労基法上の労働時間と賃金請求権は分けて考える
最低賃金法は、時間額の最低賃金のみを定めています(最賃3条)。一方で実際の賃金はそうすると,労基法上の労働時間で従来,賃金が時間給以外の日給や月給等で合意されていることも多くあります。
そして結論からいうと、例えば日給を所定労働時間数で除した金額が最低賃金の時間額以上であれば,最賃法違反は成立しません(最賃則2条)。労基法上の労働時間に含まれる特定の1時間が最低賃金以下の賃金であったとしても日給を所定労働時間で除した1時間当たりの額が最低賃金額を上回っていれば,最賃法違反の問題は生じないのです。
このように「労基法上の労働時間」と賃金請求権の問題は分けて考える必要があります。
労基法上の労働時間にあたることが後に判明した場合
実際には「労基法上の労働時間」にあたるものの、労働時間として扱われていなかった場合、その労働時間について賃金が発生するかどうかは分けて考える必要があります。しかし、もともと労働時間と扱われていなかったわけですから賃金支払に関する合意は存在しません。この場合に無給として合意されていると解釈することは妥当ではないでしょう。
このような場合には、そもそも労働と賃金が対価関係に立つという労働契約の性質から解釈して原則として賃金支払が黙示的に合意されていると考えるべきです(参考ー大星ビル管理事件・最一小判平成14・2・28民集56巻2号361頁)。
※ この記事は、執筆当時の法令や判例、実務的な運用に基づいて作成しています。また、一般的な情報提供を目的とした記事となりますので、個別の事案については法律相談をご検討ください。