離婚調停は話し合いの場だが…
協議離婚が成立しなかった場合に、最初に考える法的手続きは離婚調停です。家庭裁判所による手続であるため、訴訟のように当事者の主張を聞いて、裁判官が判断するというイメージがあるかもしれませんが、そうではなく、調停は話し合いによって合意を目指す手続です。もっとも、日常的に行われる純粋な話し合いとは異なっています。実際の調停手続きで行われる事実の調査や証拠調べについてお話しします。

職権で(も)行われる事実の調査
通常の民事訴訟では、どのような主張をし、どのような証拠を提出するかは闘技者の権利であり義務でもあります。裁判所が自主的に証拠を収集することはなく、当事者に任せておけばよいわけです。
もっとも、離婚問題については当事者夫婦だけの問題ではなく、子どもや親族に影響を与えます。そこで裁判所は、当事者だけに任せるのではなく、職権で事実や証拠の調査を行います(職権探知主義)。家事事件手続法には次のように規定されています。
(事実の調査及び証拠調べ等)
第五十六条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
このように調停での事実の調査は職権で行われるのですが、事情をよく知る当事者も調査に協力して適切で迅速な進行を実現するわけです。
調停委員や調査官、書記官による事実の調査
事実の調査は家庭裁判所が行いますが、それ以外にも家庭裁判所調査官、調停委員会の裁判官、調停委員会の家事調停委員も行うことができます。家事事件手続法の条文の一部を抜粋してみました。
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第五十八条 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。以下略
(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
第二百六十一条 調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
2 前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
以下略
(家事調停委員による事実の調査)
第二百六十二条 調停委員会は、相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
これらは職権で行われるものですから、調停の当事者が家庭裁判所に対して事実を調査するように求めたとしても、それは職権発動を促すものであり、裁判所に応答する義務はありません。当事者の立場で重要な証拠について家庭裁判所に応答してもらうためには、証拠調べの請求という手続もありますが、調停段階では事実の調査が原則となります。
家庭裁判所調査官による事実の調査
離婚調停において、よく用いられる事実の調査は家庭裁判所調査官による事実の調査です。家庭裁判所調査官になるには,裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補)を受験して採用された後,裁判所職員総合研修所において2年間研修を受けて必要な技能等を修得することが必要です(裁判所ホームページ「家庭裁判所調査官(https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan/index.html)。
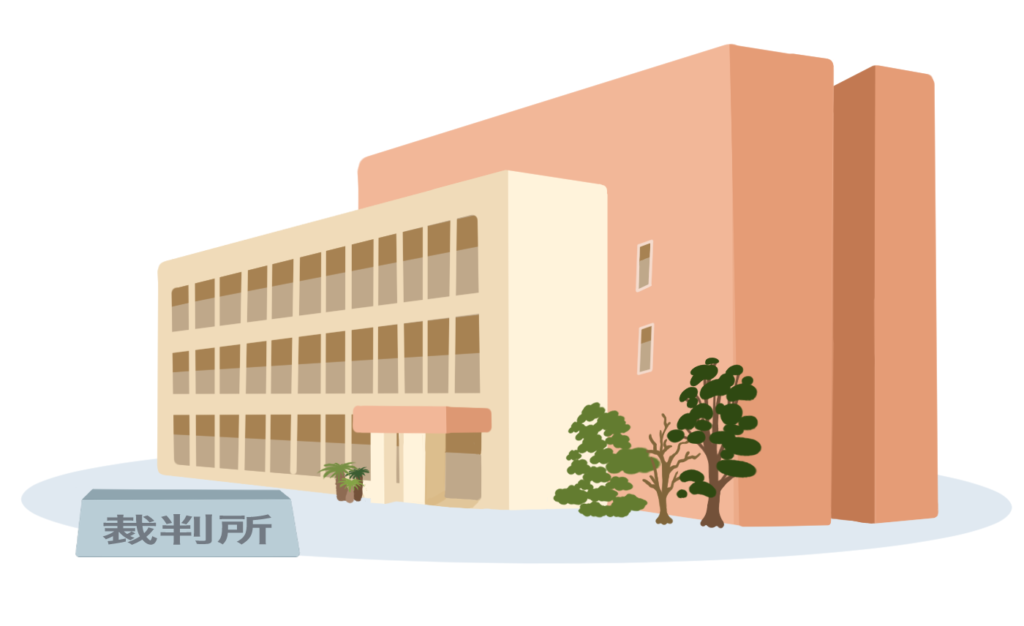
家庭裁判所調査官による事実の調査
では、実際にはどのような事実の調査が行われるのでしょうか。具定例を見てみましょう。
①親の面接による調査
離婚に際しては子どもの親権者を決めなければなりません。そこで子どもの事情、例えば生育状況や家庭での様子、親子関係など多岐にわたり聴き取りが行われます。この聴き取りをもとにさらに別の調査が行われることが多いでしょう。
②家庭訪問による調査
単に親から聴き取りを行うだけではなく、家裁調査官が家庭訪問し、子どもの様子や生育状況、生活環境などを観察して調査をすることもあります。当事者からも陳述書という形で調停の初期の段階から子どもの状況について裁判所に説明することがほとんどですが、実際に訪問して調査することでより詳しく把握することができます。
子どもと面接して親権に関する意向などを確認することもあります。
③保育園や学校などの機関への調査
子どもの家庭での様子だけではなく、幼稚園や学校での生活状況も重要なポイントになりますので調査官による調査が行われることもあります。当事者ではなく、第三者機関ということで客観的な情報が確認できるというメリットがあります。
当事者としては、母子手帳や保育園などへの連絡帳などを提出して、保育園等での様子や養育状況を伝えることも重要です。
当事者による事実の調査への協力
家庭裁判所調査官による事実の調査は、調停の初期から行われることは少なく、親権が争われ、当事者の主張がある程度明らかになった段階で行われるのが通常であるといえます。また、必ずしも家庭裁判所調査官による調査が行われるということでもありません。
そのため当事者としては、親権が争点になるケースでは、親権を定めるにあたって重要なポイントを陳述書などでしっかりと整理し、母子手帳や連絡帳など客観的な第三者機関からの情報が記載されている資料を整え、調停の期日においてしっかりと家庭裁判所に示していくことが重要です。
※ この記事は、執筆当時の法令や判例、実務的な運用に基づいて作成しています。また、一般的な情報提供を目的とした記事となりますので、個別の事案については法律相談をご検討ください。

