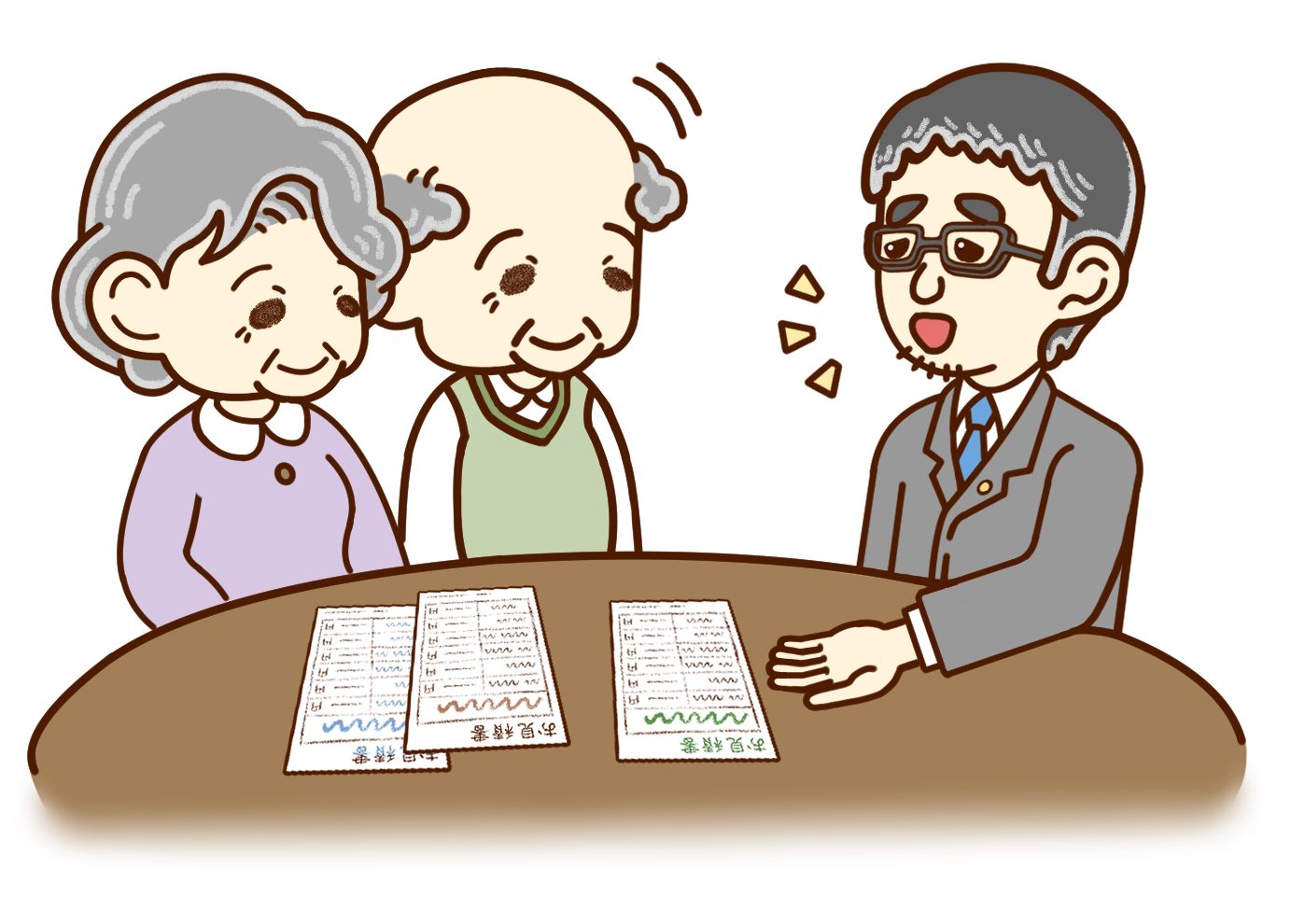成年後見人を決めるのは家庭裁判所
判断能力が低下した方に、成年後見人をつけてほしいと申立てができるのは、ご本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などです。後見制度に対するよくある誤解として、親族が申立てをする場合は、その申立人が希望する人が成年後見人に選ばれるというものです。例えば、判断能力が低下した方の推定相続人間で紛争がある場合などでは、そういった誤解から申立てに強硬に反対される方もいらっしゃいます。この記事では成年後見人がどのように選任されるのかお話します。

成年後見人を決めるのは家庭裁判所
成年後見人をつける場合には、家庭裁判所に申立てを行い、「後見開始の審判」を受ける必要があります。民法という法律に次のような条文があり、法律上の根拠のある後見制度なので法定後見とも呼ばれます。
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
成年後見人を決めるのは家庭裁判所であり、ご本人にどのような支援が必要かといったことを考慮して決められます。
申立書に記載する成年後見人候補者
後見開始の審判をしてほしいとの申立てをする場合には、申立書などを家庭裁判所に提出して行います。どのような書類なのかについては、裁判所の後見ポータルというサイトで記載例とともに公開されています(裁判所ホームページ「後見ポータルサイト」https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/index.html)(「後見開始の申立書」https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html)。この申立書には候補者を記載する欄があり、「裁判所に一任」「申立人」「申立人以外の者」という選択肢が提示されています。
もっとも、家庭裁判所はこの「候補者」に縛られることはありません。あくまで判断能力が低下した方のサポート役として適任は誰かという視点で判断されるのです。
家庭裁判所はどうやって決める?
成年後見人について、家庭裁判所は、申立書の「候補者」に縛られないとして、では、どのように決められるのでしょうか。当然ながら「候補者」として申立書に記載されている方が適任である場合も少なくありません。一方で親族間で意見の対立がある場合などでは、「候補者」をそのまま選任した場合に紛争が生じたり、スムーズに後見人としての活動が行えない場合も想定されます。家庭裁判所による選任方法について見てみましょう。
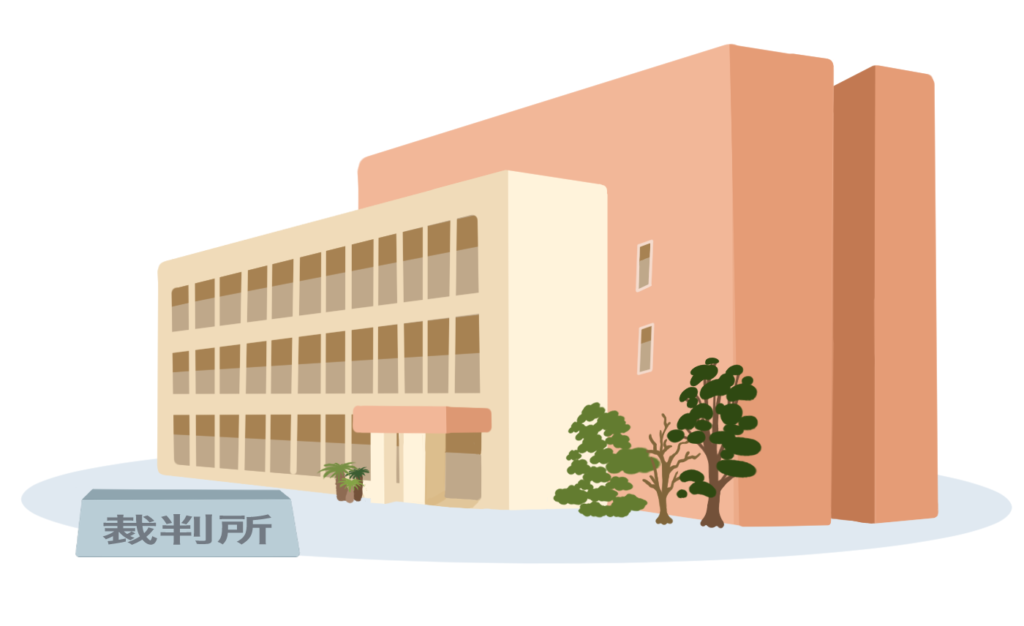
「候補者」がいないケース
申立書で「裁判所に一任」とされている場合について見てみましょう。裁判所が公開している「成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―」10頁(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20220316koukengaikyou-r3.pdf)によると、申立書に親族の候補者が記載されている割合は、23.9%です。また、親族が後見人として選任された割合は19.8%となっています。これを見るとそもそも親族が候補者とされている事案が少なく、記載されている場合にはその候補者である親族が選任されるケースが多いといえます。親族が候補者として記載されていない場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合がほとんどで、選任にあたっては、必要とされる専門的知見を有する専門職を選ぶということになります。
「候補者」が選任されないケース
「候補者」が、判断能力の低下したご本人の資産を流用したいと考えているような明らかにご本人の利益を害するような「候補者」が選任されないケースももちろんありますが、それ以外にも誰を後見人に選任してほしいかという点で意見の対立がある場合にも「候補者」が選任されない場合があります。申立てにあたっては、ご本人の推定相続人の方からの意見書も提出し、家庭裁判所が成年後見人を選任するにあたっての参考にします。また、意見書が提出されない場合には、必要に応じて家庭裁判所から書面を送って調査することもあります。このような意見書や調査によって意見の対立が見られれば、「候補者」が選任されないこともあります。
また、「候補者」がご高齢であったり、遠隔地に居住しておりサポートが難しいような場合、ご本人が「候補者」を後見人に選任することについて反対している場合などでも「候補者」が選任されないことがあります。
このように成年後見人は、家庭裁判所が「候補者」も含めて、ご本人にとって適する人を選任することになり、例えば親族を後見人として選任したうえで、専門職の後見監督人をつけるといったこともあります。
※ この記事は、執筆当時の法令や判例、実務的な運用に基づいて作成しています。また、一般的な情報提供を目的とした記事となりますので、個別の事案については法律相談をご検討ください。