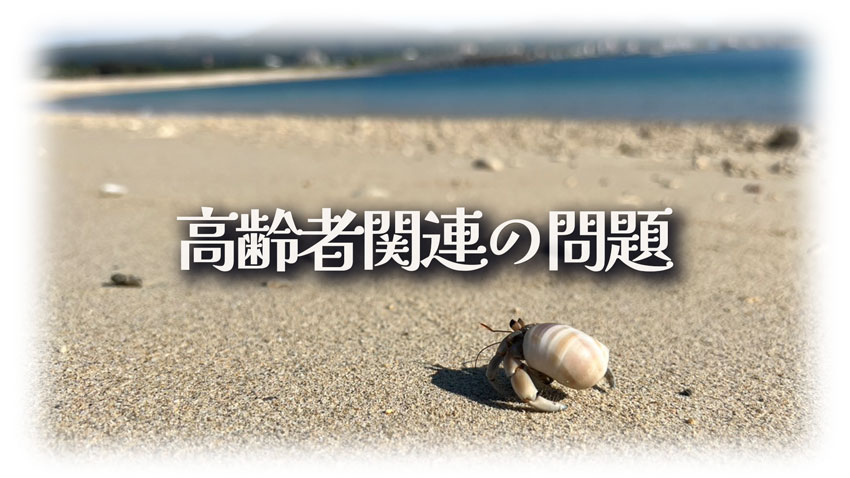ご高齢者の困りごと
認知症高齢者数は2025年におよそ700万人(高齢者5人に1人)になると推計されています。
判断能力が低下すると日常生活のさまざまな場面で困りごとが生じ、判断能力の低下に乗じた詐欺や悪徳商法による被害も懸念されます。
そのようなご高齢者の困りごとについては当事務所にご相談ください。

家族によるサポートと限界
家族による支援や事実上の財産管理にも限界があります。ご本人の意思確認が必要な契約、ご本人による不必要な契約の取消などは容易ではありません。
また、ご本人が亡くなられた際に親族による引き出しが他の相続人から疑念を抱かれて紛争になるというケースもありえます。
ご家族のサポートにも限界があるということを想定して不都合が生じる前に対策を講じておくことがご本人やご家族の安心にもつながります。
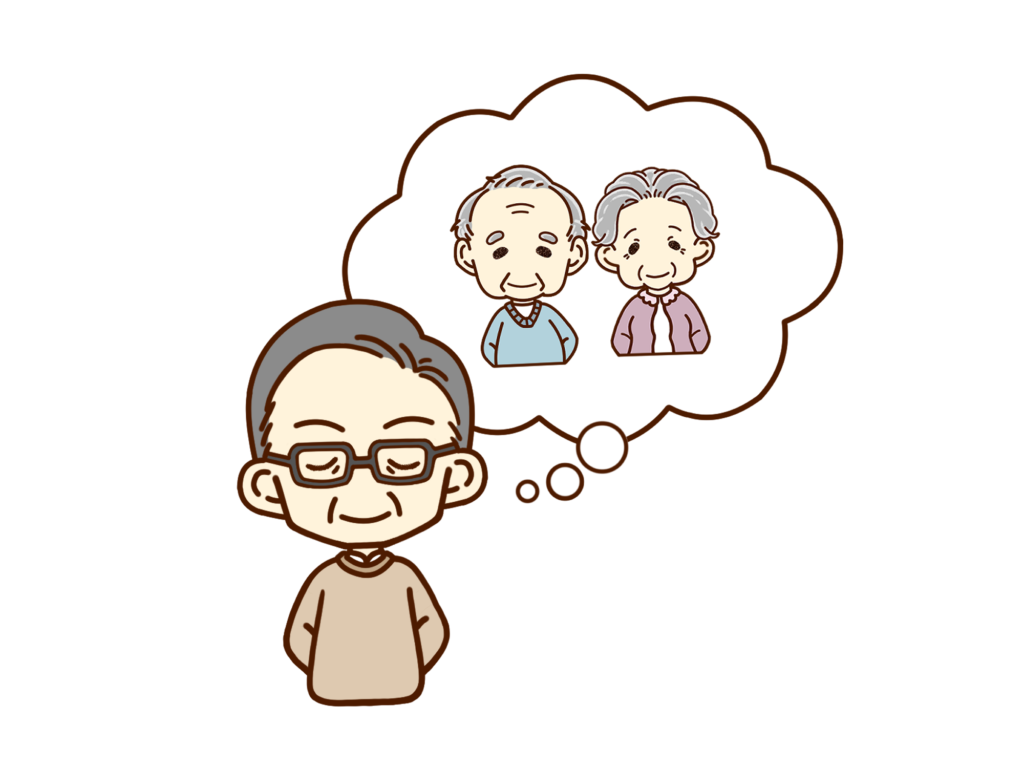
法律上の制度や仕組みを使う
判断能力が低下することは、どなたにも避けようがないことです。
そうすると認知症の予防を頑張るだけではなく、認知症となった場合の準備や対応が必要です。
そのための法律上の制度や仕組みが複数あります。ここでは成年後見制度や任意後見制度、民事信託について簡単にご紹介します。
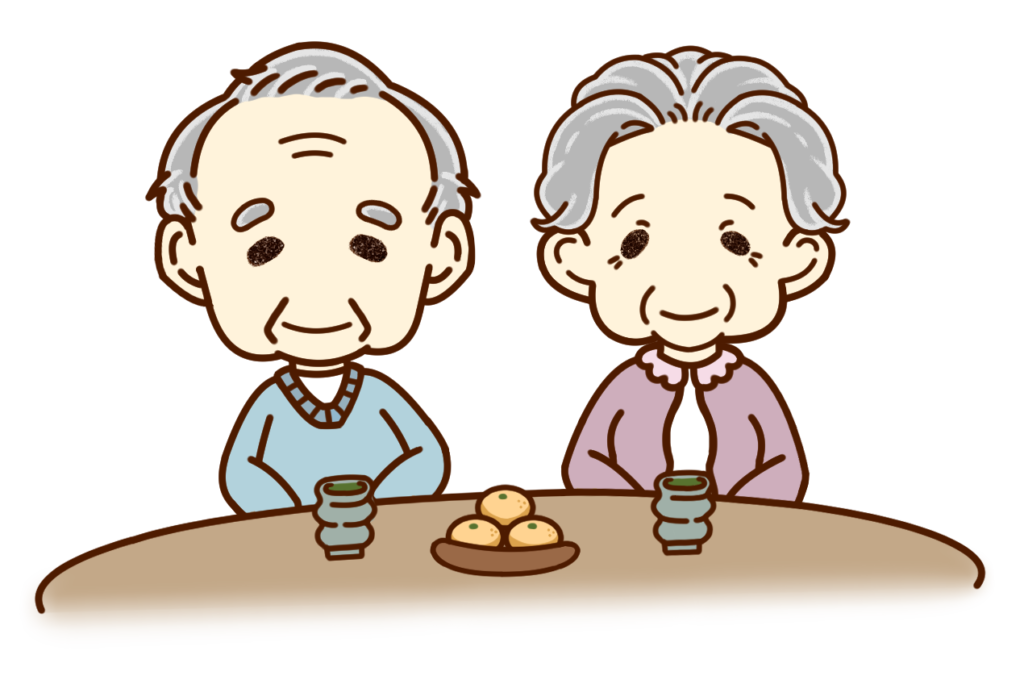
成年後見制度を使う
「成年後見制度」では、家庭裁判所がご本人の判断能力の程度に応じて支援者(成年後見人、保佐人、補助人)を決めます。具体的には、以下の表のように分けられます。
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる人 | 判断能力が 不十分 | 判断能力が 著しく不十分 | 判断能力が ほとんどない |
| サポートする人 | 補助人 | 保佐人 | 後見人 |
| サポートの内容 ※基本 | ごく一部の限られた契約・手続の同意・取消 | 重要な類型の契約や手続の代理・同意・取消 | 広範囲な代理権 ・取消権 |
※保佐の場合、さらに必要な部分についてご本人が同意し家庭裁判所が認めた代理権を追加できます。
任意後見制度を使う
法定後見は、判断能力が不十分となった段階で利用する仕組みですが、事前に準備しておきたいというニーズもあります。また、法定後見はサポートする人を家庭裁判所が決めますが、ご本人が自分でサポートしてくれる人を選びたいというニーズもあります。
そのような場合には本人の判断能力が十分なうちに「任意後見制度」を利用するという選択もあります。
| 類型 | 概要 |
|---|---|
| 移行型 (財産管理委任契約+任意後見契約) | 判断能力がある段階で、ご本人が選んだ人と①任意代理契約と②任意後見契約を結ぶ。 判断能力に問題がない段階では①により契約したサポートを受け、判断能力が不十分になった段階で②に移行(家庭裁判所に後見監督人を選任)して任意後見業務をスタートする。 |
| 即効型 (任意後見契約のみ) | 任意後見契約を結ぶと同時に家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見業務をスタートする。 |
| 将来型 (見守り契約+任意後見契約) | 判断能力がある段階で、ご本人が選んだ人と①見守り契約と②任意後見契約を結ぶ。 判断能力に問題がない段階では①により定期的な電話連絡、訪問面談などを行い、ご本人の健康状態等を確認、判断能力が不十分になった段階で②により家庭裁判所に後見監督人を選任してもらい任意後見業務をスタートする。 |
※任意後見契約は公証役場で公正証書を作成する必要があります。
家族信託を使う
法定後見や任意後見で行われる身上監護がなく、財産管理や承継に特化した仕組みとして民事信託(家族信託)もあり、法定後見や任意後見との併用も可能です。
民事信託とは、財産を引き継ぐために、信頼できる人(家族が多い)に財産の管理・処分を任せる制度です。
ご本人が委託者(財産を預ける人)となり、受託者(財産を管理する)に財産を預け(形式的に所有権が受託者に移ります)、受託者は受益者(財産から生じる利益を受ける人=ご本人である場合が多い)のために財産を管理・処分することを義務づけられます。
法定後見ではできない資産運用や処分、財産承継も行えることから広い範囲でご本人の意向を反映できます。
ちむじゅらさんの法律相談
初回無料相談(60分)
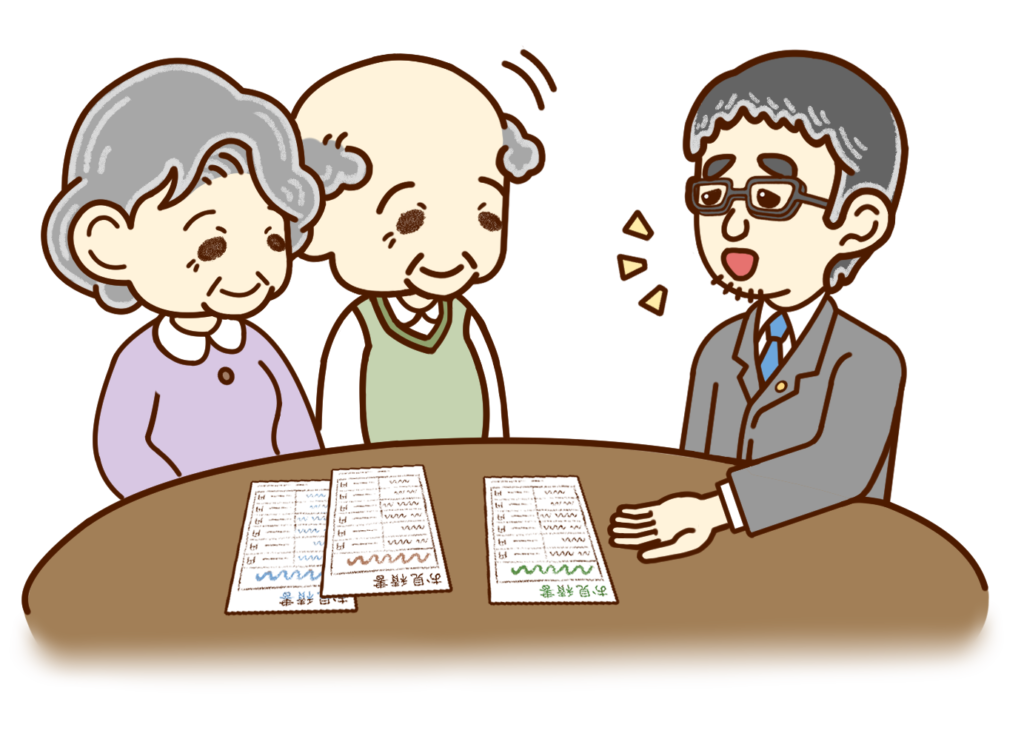
当事務所にでは、ご本人やご家族のお悩みや将来への不安を丁寧にお聞きし、ご本人やご家族の希望が可能な限り実現できるような仕組みや制度の組み合わせなどをご説明させていただきます。
仕組みや制度の概要を知ることで、選択肢は広がり、納得した選択や準備をしていただけます。
当事務所の弁護士は、法テラスの契約弁護士です。認知機能が低下してご本人では法律相談の予約が難しい場合には、支援者・関係機関の皆様からご予約いただき、出張相談をさせていただく法テラスの特定援助法律相談がご利用いただけます。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
弁護士費用の目安

ちむじゅらさんに依頼した場合の弁護士費用の目安は以下のとおりです。ご本人の判断能力やどのような仕組みを使ってサポートするかによって異なりますので、詳しくはご相談時にご説明します。
| 委任内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 成年後見等 申立て | 22万円〜 | なし |
| 任意後見 契約書作成 | 契約時:22万円 後見監督人選任申立時:11万円 | なし |
| 任意後見人 月額報酬 | なし | 月額5500円〜 ※管理内容等によります |
| 家族信託 契約書作成 | 22万円〜 | 44万円〜 |
※当事務所の弁護士が任意後見人をお引き受けする場合の契約書作成費用は11万円です。
※公正証書を作成する場合、公証人に対する報酬として公証役場所定の公証人報酬が必要になります。
※金額はすべて税込金額です。